-EP.35- 今年度の現任教育終了と警備員教育の方法について
1.はじめに
今月22日までに、法定の令和6年度における現任教育を終えることができました。
受講された各位には、県外業務等が混み合う勤務日程を調整されての受講となりましたが、本講義を、終始、熱心に聴講して頂きまして改めて感謝を申しあげます。
この講義で得た知識などが、平素の業務にも反映され、業績向上や社会貢献につながることを願っております。
2.警備員教育の方法について
警備員教育の方法については、従来、法定の新任教育、現任教育とも、警備員指導教育責任者(警備員教育を行う者)が、受講者と対面して「講義式」、「実技訓練」及び「実地訓練」により実施することとされてきましたが、令和2年頃から猛威を振るったコロナ禍の教育対策として密集しない教育方法として、電気通信回線を用いた「eラーニングによる講義」が注目されてきていますのでご紹介します。
この方式は、令和元年8月30日公布された警備業法施行規則の一部改正で、第38条第2項及び第3項の表の備考中に、「講義の方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う方法(電気通信回線を使用して行うものを含む。)とする。」と盛り込まれたことにより可能となった経緯にあります。
講師と受講者が非対面となるこの講義方法には
〇パソコン等でインターネットを利用した通信学習方式
〇インターネット回線を用いたオンライン会議システムを利用した遠隔講義方式
があります。
なお、この「eラーニングによる講義」が、法定教育と認められるためには条件があり、対面式による講義と同等の教育効果が得られることと、次の要件を満たす必要があります。
※要 件
① 受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。
② 受講者の受講状況を確認できるものであること。
③ 受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること。
④ 質疑応答の機会が確保されているものであること。
3.おわりに
近年の、情報通信技術の発達により、テレビ会議システムを利用して、遠隔地にいる者に対する教育を行うことが出来るようになりました。
全国警備業協会等では、「eラーニングによる講義」は、パソコンやスマートフォンで受講することができるので、インターネットにつながる環境さえあれば、いつでも、どこでも警備員教育は可能であるとして推奨していますが、この方法は、実技訓練や実地訓練には対応できないことや、受講者に対する本人確認のための受講開始前の生体認証の実施、受講状況の確認体制などクリアすべき諸課題があることに留意が必要です。
担当:茶山顧問


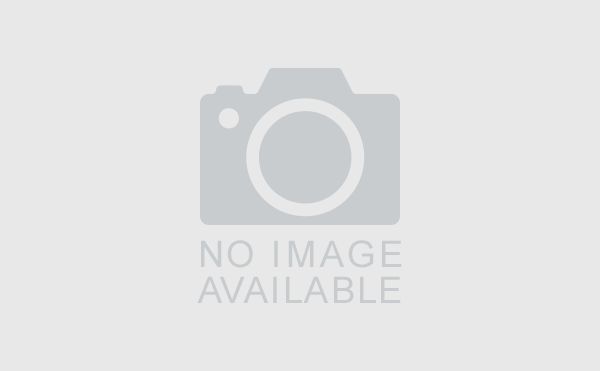
 / 警備室たより 著者プロフィール
/ 警備室たより 著者プロフィール